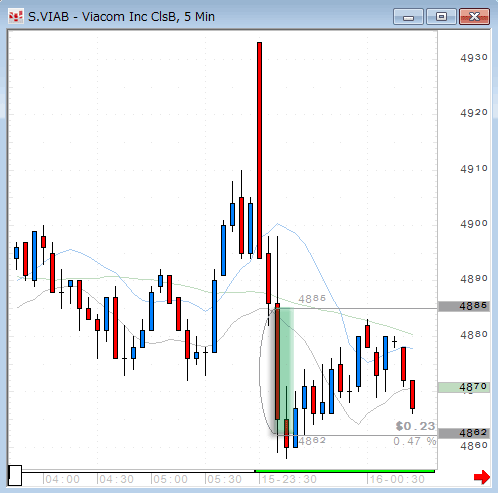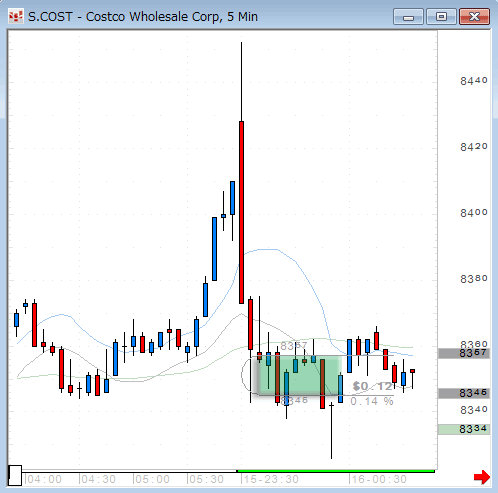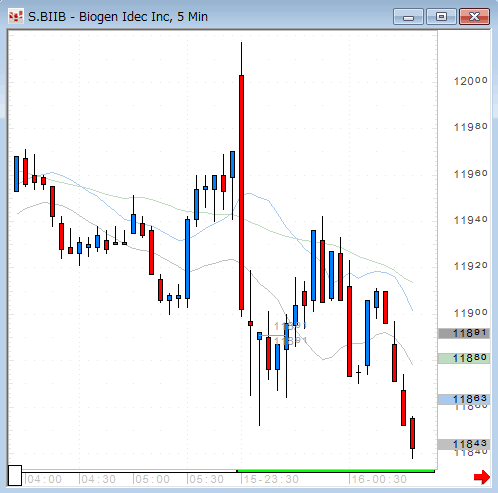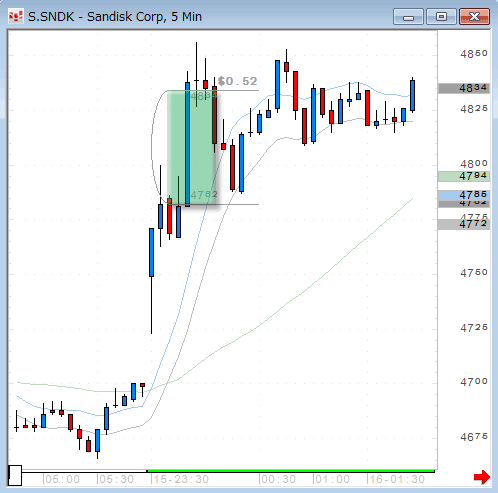本屋を訪れると溢れんばかりに本が並べられているが、依然として出版不況は深刻な状況が続いている。
特に雑誌の部数減が止まらず26年ぶりに1兆円割れ。

発行部数で言えば35年ぶりに20億冊を下回っている。
97年比で販売額は37%減、95年比で販売部数は49%減。
月刊誌が4割減、週刊誌が6割減で、週刊誌の方が減り方が激しい。
出版業界の規模は業界の中でどれくらいに位置しているかご存知だろうか?
下記はそれぞれの分野のトップ企業一覧だ。
メディア・IT関連の上場企業
固定通信業界 日本電信電話 【10兆3050.03億円 (2011/03/31)】
音楽制作・芸能プロダクション業界 ソニー 【7兆1812.73億円 (2011/03/31)】
映画製作・配給業界 ソニー 【7兆1812.73億円 (2011/03/31)】
移動体通信業界 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 【4兆2242.73億円 (2011/03/31)】
総合広告代理店業界 電通 【1兆8334.49億円 (2011/03/31)】
ゲームソフト業界 任天堂 【1兆0143.45億円 (2011/03/31)】
テレビ放送業界 フジ・メディア・ホールディングス 【5896.71億円 (2011/03/31)】
出版業界 ベネッセホールディングス 【4128.28億円 (2011/03/31)】
ポータルサイト業界 楽天 【3461.44億円 (2010/12/31)】
Eコマース業界 楽天 【3461.44億円 (2010/12/31)】
携帯・オンラインゲーム業界 コナミ 【2579.88億円 (2011/03/31)】
ネット広告業界 サイバーエージェント 【1195.78億円 (2011/09/30)】
SNSサイト業界 ディー・エヌ・エー 【1127.28億円 (2011/03/31)】
音楽配信業界 エイベックス・グループ・ホールディングス 【1115.61億円 (2011/03/31)】
イベント企画・運営業界 乃村工藝社 【901.05億円 (2011/02/15)】
モバイルコンテンツ制作・配信業界 フェイス 【841.91億円 (2011/03/31)】
アニメ・映像制作業界 東北新社 【605.73億円 (2011/03/31)】
専門情報サイト業界 エイブルCHINTAIホールディングス 【464.34億円 (2011/10/31)】
出版社別売上高ランキング(事業別ではなく会社全体の売上高)
01位 ベネッセホールディングス 【4128億円 (2011/03/31)】
02位 角川グループホールディングス 【1400億円 (2011/03/31)】
03位 ぴあ 【926億円 (2011/03/31)】
04位 学研ホールディングス 【802億円 (2011/09/30)】
05位 ゼンリン 【528億円 (2011/03/31)】
06位 エイブルCHINTAIホールディングス 【464億円 (2011/10/31)】
07位 プロトコーポレーション 【287億円 (2011/03/31)】
08位 昭文社 【152億円 (2011/03/31)】
09位 インプレスホールディングス 【151億円 (2011/03/31)】
10位 文溪堂 【108億円 (2011/03/31)】

1990年代半ばまでドル箱だったコミックは、少子化の影響をモロに受けて不振で、携帯電話やインターネットによる情報収集が追い討ちをかける形で、読者の活学離れが進んでいる。
既存出版物は落ち込んでいるが、ベネッセ、ぴあ、角川グループ、ゼンリンなど出版物以外に強みを持つ企業の業績は堅調だ。
ベネッセは通信教育「進研ゼミ」、ぴあは情報・チケット販売、角川グループはクロスメディアコンテンツの提供、ゼンリンはカーナビなど地図データベース事業を展開している。
2000年に約2万2000店あった本屋は、2010年には30%近く減少して、1万5500店へと減少。
インターネットの普及により、若者を中心とした「活字離れ」はますます進行しているようだ。
今後も、既存出版物の売上の減少は続くものと予想され、出版業界に大きな変化が押し寄せている。
さらにレンタル書店や新古書店の台頭など、決して先行きは明るくないようだ。
しかもこの業界は返本率が高く何と40%越え。
つまりで売ったものの4割がゴミになるわけだ。
著者への著作権料や、印刷コストなどは刷り部数で決められているため、この返本率の高さが出版社の経営を大きく圧迫している。
2007年の時点で、出版社の平均経常利益率は何と、3%を切る 2.6%。
一般管理費が捻出できなければ土俵にさえ上がれないわけで、新刊のうちの半数を占める初版のみの本は、ほとんどが外注費による原価のレベルですでに赤字、という状態なのだ。
出版社の収益構造は、書籍の小売価格100%のうち、書店と取り次ぎで30%、残りの70%が出版社の取り分。
出版社の取り分の内訳は以下のとおり。
・著作権料10%
・印刷20%
・デザイン10%
・販売費10%
・管理費10%
・出版社の利益10%
重版では製造原価が下がるため利益率は高くなるものの、返本率が40%にもなので、このままだと赤字となるわけだ。
現在の出版社は、返本率の低い一部のヒット作でなんとか凌いでいるというのが現状。
不況になると、当然ライターや作家の原稿料は悪影響を受けることになる。
部数が出ないと、どうしても粗悪乱造状態になりやすく、資産家あるいは別に職をもつ大学教授や天才作家以外、不況であればあるほど、ダンピングの影響をモロに受けることになる。
そのため、下請けの仕事からますます抜け出すことができなくなるというわけだ。
また他の仕事と大きく異なる点は、人件費に相当する原稿料が、40年前からほとんど変わっていないという点だろう。
「メディアアクセスガイド・現代人文社」には133紙誌の原稿料相場が掲載されているが、何と95%が400字単価換算で1000円から1万円の中に収まっている。
これには作家自体が原稿料にこだわらないことを、むしろ誇りにする風潮という、日本独特の体質が残っているため、ますます「質」や「速さ」を度外視することになるのだという。
個人事業主という観点で見ると、多くのライターや作家は、いわゆる潰しの利かない書くだけの技術しか持っていない零細企業だといっても過言ではないだろう。
こうした理由で基本的な経営や経済観念に対するセンスが備わっていないことが多く、余計にこうした傾向に拍車がかかるというわけだ。
情報収集の手段は世界的に紙媒体からネットへ移行し、雑誌広告の収入が落ち込んでいるという時代の流れにモロ巻き込まれた格好だ。
また出版業界自体が媒体にこだわらない情報サービス系と従来型の出版会社に分かれ始めているため、出版社にとっても、出版の枠組みの設定目体が難しくなってきているという事情も絡んでいるようだ。

では欧米ではどういういう仕組みで動いているのだろう?
アメリカやヨーロッパでは本と雑誌の流通はきちんと区別され、本の出版社と書店の間で、電話などでの直接注文が行えるしくみが完備されている。
取次のような流通会社も存在しているが、出版社と書店が互いに在庫を確認し、すぐに注文できるような体制になっているのだ。
本は雑誌とは別の流通システムで、出版社直営か代行業の卸売会社が全体の70%の流通を司っている。
取次は存在しているが、補助的な流通プラットフォームでしかないのだ。
何よりも重要なのは、アメリカやヨーロッパでは、本は書店の買い切り制になっていると言う点だ。
そのため欧米では、無駄にたくさんの本が書店に送り込まれるようなことはなく、書店が必要する本だけが注文され、出版社から書店に送られてくる仕組みになっている。
ところが日本では、「どうせ委託だから売れなければ返本すればいい」という無駄なシステムで運営されている。
そのため、バカみたいにたくさんの本が毎日毎日、出版社から取次を経由して書店に集中豪雨のように流し込まれるというわけだ。
書店側は、アルバイトを雇ってせっせと毎日毎日、膨大な本を取次に返本するという漫画のようなことが行われている。
だがこのシステムは資源の単なる無駄遣いだけでなく、委託制による大量配本は、別の重要な問題を出版業界に引き起こしている。
それは「本のニセ金化」と呼ぶ現象だ。
書店と取次、出版社の間のお金のやりとりは、さまざまな条件があり非常に複雑だが、単純化して説明してみよう。
定価700円の新書の場合、出版社から取次に卸す金額は500円ぐらいで、仮に1万部刷って、出版社が取次に卸したとする。
この際に売れた分だけ取次からお金をもらうのではなく、取次に委託した分すべての金額をいったん取次から受け取れるわけだ。
新書を取次に卸すと出版社はいったん取次から500万円のお金が支払われることになる。
もし1万分のうち書店で5000部しか売れず、残り5000部は返本されたとする。
当然のことだが出版社は、この5000部の代金250万円を、取次に返さななければならない。
すると出版社は別の本を1万部刷って、これをまた取次に卸値500円で委託。
その売り上げ500万円から、返本分250万円を差し引き、250万円を相殺した分が収入となるわけだ。
この「本のニセ金化」と呼ぶ仕組みによって出版社は返本分の返金を相殺するため、本を紙幣がわりに刷りまくる、という悪循環に陥ってゆく。
こうしたいわゆる「粗製濫造」サイクルに陥ると、書かれている本の内容というかレベルは落ちてゆくことになる。
そうなると読者は似たような内容の本ばかりに飽きて、だんだん本を読まなくなるというわけだ。
「本が売れなくなっている」というのに本の出版点数は80年代と比べると3倍近くにまで増えているのは、このニセ金化現象によるもの。
本が売れない > 返本が増える > 取次に返金しなければならない > だったら本をとにかく出し続け返金で赤字にならないようにしよう
ますます刷る > ますます売れない > いよいよ赤字が心配 > だったらもっと刷ろう
こうしたバカげた自転車操業的なスパイラルが繰り返され、無間地獄に落ちているのが、今の日本の出版業界なのだ。
誰か止めてやってくれ!(笑)